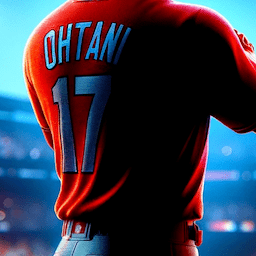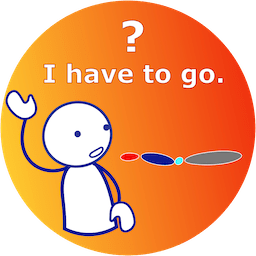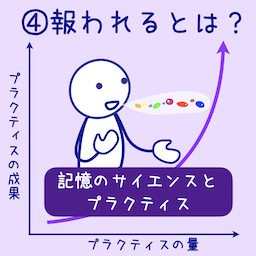いますれば、やり直せる (何度でも)
物事は丁寧にすることで身につきます。でも、つい、めんどうくさいところを端折っても、たいした影響はないだろう、と考えたりするもの。数秒のことなのだけど、それができない。あとでちゃんとやるから、大丈夫。でも、そうはなりません。「いま、しっかりすれば、また後でもやり直せる(何度でも)」そう、声に出す習慣ができると、効きます。
If you don’t have time to do it right, when will you have time to do it over?”