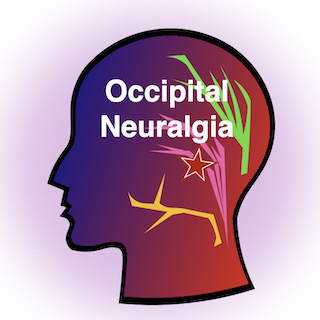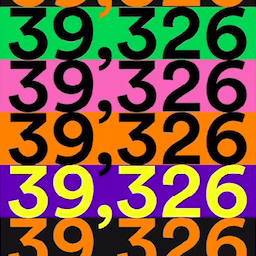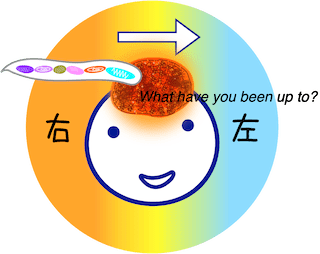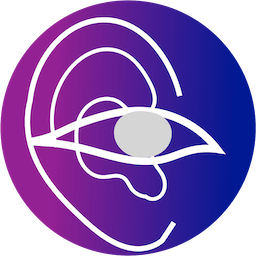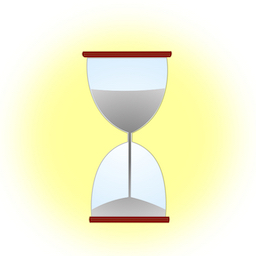Life is adventure. (5) (未知を愛する練習が人生の核心)
「心から愛することだけが乗り越えられる」と、リオネル・メッシ選手は言います。十分に愛することしか、乗り越えられないのはなぜ?あきらめてしまうからです。頭で考えたら苦しいことは止めるほうが合理的に決まっています。練習を愛することです。十分に練習が好きになれば乗り越えられます。「うまくいかない」ことを大切に思うことです。
I love what I do. I love being in training.(練習が好きなんだ)