
その頃から、アルマデンの廃鉱をよそ目にして、シリコンバレーはコンピュータ・ハイテク産業の要衝として急速に発展しだした。
コンピュータとは、計算する機械、手順のこと、その「ものとしくみ」である。
地殻で酸素の次に豊富な元素であるケイ素を地表の砂から採りだし、それを基にして集積回路をつくる。片方向にのみ移動するという電子のふるまいの特徴を引き出して、ひたすら計算する小さな回路が組み合わされてできている。
より小さく、より速く、よりたくさん。計算量は多ければ多いほどよい、微細加工は小さければ小さいほどよい、とされる。金銀や水銀などの重金属の 採掘と違って、シリコンの原料はいくらでもあり、直接的な人体危険を伴う利用というイメージは持たれていない。
電磁気という自然のふるまいを取 り出して活かす「恩恵」の、そのまた上に、電子の粒の動きを計算回数の量にみなした、その働きの上に現代文明社会は築かれている。
好むと好まざ ると関わらず、そのしくみからやって来る「特典」を受けて暮らしている。生身の人間が心身のふるまいをつくる技術はアートと呼ばれ、その拡張・延長、応用はテクノロジーと呼ばれる。人間の創造性という特徴を外側に広げたものである。

しかし、今やそのテクノロジーが先導する現代文明の姿 は、息がつまるほど性急で、著しく過剰で、実に複雑になってきている。それなのに、ふつうの日常生活を暮らす私たちにとって、人間の身の丈で想 像できる範囲を飛び抜け、その姿の全体像がますます見えなくなっている。一方、人間の「いのちのリズム」は昔から少しも変わっていない。
呼吸をするひとつひとつの間合いに、何かが感じられ、何かが表される、という 繰り返しのリズム。自然な身体のふるまいと、何かに触れては湧き上がる「思い」とが途切れることなく連なっている。その「連続体」が生きている ことである。その「持続」そのものを、私たちは生きている。
しかし、人間は、桁違いのスピードで考えたり、手足を動かしたりすることはできな い。突然に大量の思考をすることはおろか、急かされた瞬間にじんわりと感じることもできない。

私たちは、ひと呼吸ずつ、順に、生きている。だか らいろんな仕事を機械に「やらせる」のだといっても、結局、生きるのは自分だけである。誰もこの身の代わりに歩いたり、感じたり、夢を見たりすることはできない。だれもがみなそうである。
便利で快適な生活は果てしもなく追求するものだと言われても、過剰な「供給」がいつまでも「需要」 を生み出し続けるしくみが無限に続くとは思われない。そもそも、とても消化吸収のできないような摂取や、放埓で無制限の過剰を供給と呼ぶことはできない。
人間には超えられないものがある。生命体の身体は、そうしたバランスをとることによっていのちを紡ぎ、繋いでいることを、本来、私たちは身をもって知っていたはずである。現代社会は、過剰というものの姿が見えず、声が聞こえず、肌で触れて気がつくという機会がなくなっているのだ。
過剰が無理やり需要を生み出そうとしていることに、私たちは無頓着で無関心で、無自覚になっている。それを思い出すことばが欠乏し、思い 出す力が衰弱している。時々現れ出てきても身につかず、正面からそのひとことをあげる勇気が過剰に押しつぶされそうになる
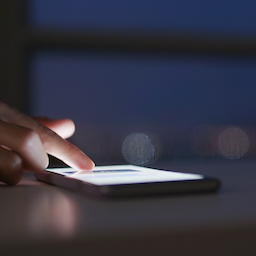
古来より、人間は資源の獲得をめぐる争い、発見と創造による繁栄と衰亡を繰り返してきた。文明はいつの時代もその過程であり、産物である。
繁 栄は過剰を生み、過剰は依存を生む。依存は惰性を生み、いつしか肝心なものが押しやられて不足する。不足は欠乏となり、最後は枯渇し、そして風化する。
物の過剰、情報の過剰、意識の過剰。
心のないことばの過剰で人を傷つけ、囚われた「私」中心の意識の過剰で苦しむ。その過剰の裏側にあるのは、想像力の欠乏である。過剰の代償と言い換えてもよい。
過剰への依存が惰性となる時、最も肝心な「想像の営み」が失われているのだと思う。とりわけ、共感という人間の存在にとって最も根源的で本質的な力が欠乏する。

共感の精錬 (9) 共感の力と本質的な問い へつづく
共感の精錬 目次ページ へもどる




![実感の訪れ [壊れるからわかること]](https://ja.empatheme.org/wp-content/uploads/2021/09/614-150x150.jpeg)