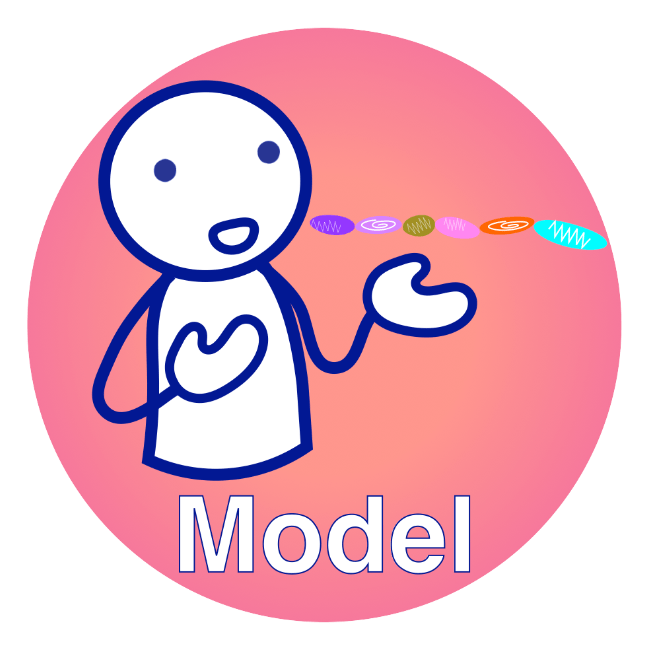エンパシーム:
無意識の制約を力に変える
知っていても、うまくできない。
そのギャップが脳のブラインドスポット。
自己流のクセは脳に過剰な負荷をかけます。
補助し、ブラインドスポットを減らします。
壁を未来への扉に変えます。
学びの最大の壁は、じぶんの無意識。
意識することのない、瞬時の身体の動き。
「習得技能の4段階」のようにはいかない
一般的な学習観として知られる「学習・能力の4段階」の中に本質的な課題が潜んでいます。
① 何ができないのか気づいていない
② できないことに気づいている
③ できることを知っている
④ 意識せずにできる
このように整理すると、①から順に進んで④に到達するかのような錯覚があります。現実は、このような直線では進みません。
従来の学習観は、課題に対する学習者の意識的な努力による知識獲得と達成率にフォーカスし、②→③の領域に限定されています。
従来の学習観ではカバーされないこと
「考えずにできる、ふるまいを無意識化する」④のレベルには、なかなか到達しません。大きな壁があります。一般的にそれは個人の資質や膨大な努力、つまり、限られた人にしかできない特別なものとして扱われがちです。
その一方で、①は著しく過小評価されています。というより、一般的な学習観から切り離されています。それは意識できない領域にあるからです。しかし、意識で捉えられないことに、じぶんひとりで気づくのは至難です。ここに、これまで見過ごされてきた、学習の大きな課題があります。
言語の運用は、無意識プロセスにある
エンパシームは、従来の学習観でカバーできない①へのアクセスし、そこから④への着実な道をつくるプラットフォームです。
音声を含む無意識のプロセスを再現性よく生成し、データ化、単位化、視覚化し、そのフィードバックを使ってくりかえし再現して身につけることができます。
ふだん、気づくどころか、考えることもないのが、ことば(発話も言語処理も)が無意識プロセスだということです。
じぶんは「何の処理能力が身についていないのか」具体的に気づける
言語の運用は運動能力です。そして、その運動に伴う脳の処理能力です。
スポーツと同じように、1秒という短い時間に身体を連続的に動かし、脳がその速さで情報を処理できることです。
文字に依存した知識量では、この能力は測れません。
図中①のUnconscious Incompetence(自覚していない、能力の欠如)の本質は、じぶんにはどの「運動能力+脳内処理能力」が身についていないかに、気づいていない、という状態を指します。
「じぶんには知らない知識があるだろう」という意味ではありません。
「じぶんで気づく力・ふるまう力」を使う
エンパシームは、音声を含む無意識のふるまいを流れで捉えたセンシングデータによって、プラクティスそのものを測ります。
そのフィードバックによって、①にじぶん自身で気づき、音でことばを処理する能力を身につけていきます。
無意識のふるまいと言っても漠然としていますね。そこで、その典型的な実例を示しましょう。
意識のブラインドスポットとは?
日常、見ているつもりでも、見えていない盲点があります。聞いているつもりでも、聞こえていない音もあります。
文字ならよく知っている単語なのに、聞き取れない、といった言語学習のブランドスポット。
じぶんの脳の働きなのに、気づけない対象、それがブランドスポットです。
じぶんの肉声を視覚化・データ化
エンパシームは、あなたの言語学習のブラインドスポットを解決します。
意識のブラインドスポットに気づくと、その原因となっている習慣的なブラインドスポットにも気づけるようになります。
いくら学ぼうとしても、教わっただけではなかなかできません。
何がジャマをしているのか、根本原因に順に気づき、自覚できることがあなたの学習の新しい道がひらきます。
それを端的に示すのが第二言語学習です。
無意識とは?
人間に備わる最大の力は無意識にあります。といっても、何か秘められた特別な力ではなく、ふだんの心の働きです。
研究によると、無意識は私たちの精神活動の95%を占めています。歩いている時、食べている時、話している時。それらの身体動作の最中に、ほとんど意識されない心理過程があります。
「じぶんの無意識」なのに、活かせない?
私たちは気づかずに無意識を使っています。でも、直接、意図的にアクセスできません。具体的に捉える方法がないために、無意識の力を十分活用できずにいるのです。
脳科学や認知科学をはじめ、人間の意識に関する知識は十分にあります。また、内面に意識を傾けて気づきを促す「マインドフルネス」も知られています。しかし、日常の「じぶんの無意識」を取り出して、具体的に役立てる方法がありません。
「意識して気づく」ことはできない
禅のプラクティスは、心の深い部分に触れる誘いをしてくれます。が、一般の私たちにとって「気づいていないことに、意識して気づく」のは至難の技です。むしろ通常、話は逆で、気づいた時に意識できるのですから。
「無意識のじぶん」はどうしたら活かせる?
スマホでAIが自在に使える時代。でも、肝心な「無意識のじぶん」を入力することはできず、「答え」を教えてもらうわけにもいきません。人はことばでは説明できなくても多くのことを無意識的に知っている、「暗黙知」という概念はあるのですが、具体的にはどうすることなのか、わかりません。
エンパシームとは?
エンパシームは、この問題を解決する、画期的な発明です。「じぶんの無意識」をデータ化して、広く活用するメソッドとテクノロジーです。無意識に起こるプロセスを再現性よく生成し、その流れをデータとして捉え、単位化し、視覚化し、構造化します。
無意識を発揮させる流れをつくる
無意識を発揮させ、それがふるまいに表れるような状況をつくり、デジタルデータとして取り込むことで利用するのです。
エンパシームを使うことで、ふだん気づいていない、自身の無意識のふるまいに気づき、また意識せずにプラクティスの継続性を高められます。
「じぶんの無意識」を取り出して使う
無意識の力を引き出すことによって、学習プロセスをより円滑に、より楽しく、学んだことを内面化(身につける)できます。
「他人の意識を研究するデータ」としてではなく、日常のじぶんが意識していないことをに気づき、それを具体的な学びに役立てて成果を実感するために編み出されました。
無意識を捉えるアプローチ
エンパシームは、無意識に起こるプロセスを二つのレイヤーに分けて捉えます。
レイヤー①は、私たちが意識することなく起こる、暗黙の習慣的プロセスです。
レイヤー②は、身体動作に伴う自動的な認知プロセスで、リアルタイムで捉えるにはあまりに速い、1秒以内の動作に伴います。
無意識に起こるプロセスには、異なる時間軸があります。長期にわたって形成される無意識プロセス(習慣形成など)と、ある短期時間に起こる無意識プロセス(身体動作の反復など)です。
ふたつの無意識レイヤーの関係
通常、レイヤー①の中で、レイヤー②のプロセス、すなわちスキルを身につけるために必要な反復的な身体動作などが起こります。
そして、レイヤー②のプロセスは、周期的にくりかえすことで、レイヤー①を強化できます。 意識しないでも自動的に身体が動くようになることが「身につく」ことです。すなわち、無意識化され、脳の処理スピードが速くなります。
無意識へのアクセス
静かにすわって息を吐き、肉声でことばを発するなど、慣れると意識せずにできる行為をくりかえすことで、レイヤー①と②の両方があわさって無意識が自然に発生する場をつくります。
二つのレイヤーアプローチによって、データを取り込み、パターンを視覚化し、自分の行動をふりかえることができ、ふだんは「意識されない、あるいは意識できない」情報へアクセスできます。
インナー・スピーチとは?
無意識の最大の資源は、インナースピーチです。インナースピーチとは「脳内で再現されることば」。
肉声を発することで、ことばは身体化されます。無意識の中に蓄積され、再現され、思考や感情を形づくる、貴重な「心の資源」になります。
エンパシームは、無意識の力を最大限に発揮し、インナースピーチ化を促進して、学びの原動力を培います。
肉声がインナースピーチを育てる
インナースピーチは発声のプロセスを通じて形成されます。セリフを思い出し、声に出したり聞き入れたりするたびに「音の列」が対応するイメージとつながって脳内に再現されます。
くりかえす体験により、ことばは徐々に内面化され、脳内で静かに発声できるレベルに到達すると、音列のイメージがくっきりと具体的に感じられるようになります。
インナースピーチは、脳の再現力
この過程で、神経のつながりや経路が発達し、記憶からフレーズを素早く簡単に取り出すことができるようになります。 言い換えると、インナースピーチは「再現力」です。
母語と第二言語のちがい
母語であれば、このプロセスは幼児期に起こります。一方、第二言語の場合、学習者には、はじめ、そのことばのインナースピーチがありません。つまり、ゼロから構築していくことになります。エンパシームは「白紙状態のインナースピーチ」から始める、という点に着目します。
インナースピーチは、第二言語習得の推進力
第二言語学習は、意識的な行為だと思われています。ところが、実は、主に無意識によって促進されるプロセスです。
無意識の力を引き出すことが、第二言語習得の最大の原動力です。
多くの研究で、第二言語の習熟とインナースピーチの能力にはかなりの相関があることが明らかにされています。
ワーキングメモリの制約で処理能力をあげる
インナースピーチは、言語要素をより速く処理し、記憶からより効率的に取り出すためにクリティカルです。
わずか1-2秒で言語処理をするワーキングメモリ(脳の作業記憶)の容量や処理速度をはじめ、二つの無意識レイヤーでの脳内プロセスに関わっているからです。
また、母語のインナースピーチは、その多くが無意識化しているため、測定がむずかしいところ、第二言語学習におけるインナースピーチは、エンパシームを用いれば、発展の過程や度合いを測ることができます。
すでに身につけている母語のパターン
従来、インナースピーチ化の過程と度合いを捉えて、その促進と育成に着目したメソッドやテクノロジーはありませんでした。
それは、第二言語におけるインナースピーチの促進には、学習者がすでに身につけている、無意識レベルの母語発話パターンに、じぶんで気づく必要があるからです。
脳に染みついていて、じぶんでは気づかないことを「忘れる」 (Unlearning)といっても容易ではありません。脳内に取り外す「もの」があるわけではありません。新しいパターンをくりかえしまねて、質の高い「脳内再現」の頻度を上げることが不可欠です。
無意識レベルの壁がある
日本人の英語学習の課題は、知識の不足ではありません。まず、手本を声に出して再現する(まねる)プラクティスの頻度が極端に少ないこと(量)と、まねの仕方(質)に見えない壁があります。
母語の音やリズム、読んで単語の意味を理解する「文字への依存」など、記憶に深く根づいたパターンがあります。
無意識のレイヤー①②で、じぶんでは気づけないクセがあり、意識しようにも速すぎて(時間が短すぎて)捉えきれません。
本質的な課題は、意識されていない壁を徐々に取り除く(母語のクセから切り替えられる)ことなのです。
壁を取りはずす
無意識のうちに抱えていることが、第二言語習得の妨げとなり、インナースピーチ習得の大きなハードルになります。
また、従来の第二言語教育は、インナースピーチの発達よりも、第二言語の語彙や文法などを母語に変換し、読んで理解して学ぶという意識的な、知識獲得面に重点を置いています。
「読んで意味がわかるから簡単だ」と受けとっていることの中にも、無意識的な落とし穴があります。
まねているつもりでも、実はまねていない、といったことが、気づかぬなところで起きます。
「できていないこと」で成果を出すことはできません。無意識レイヤーでの壁に気づけるような仕掛けがいります。
インナースピーチの発達を測る
エンパシームは、無意識に起こるプロセスをふたつのレイヤーで捉え、インナースピーチの発達過程を持続的、効果的に測定し、有益な気づきのヒントを提供することで、この問題を解決します。
第二言語学習の重要な側面は無意識の中で起こっているため、この情報を捉え、再利用する有効な方法を見つけることが不可欠だからです。
じぶんの無意識を対象化
無意識は、目に見て触れられるものではありません。従って、無意識を対象化することで、無意識に起きるプロセスや情報を効果的な言語学習に取り入れるという考えが必要になります。
比較するから気づける
エンパシームは、学習者が確認できる正確で詳細なフィードバックを提供し、ネイティブスピーカーの例と自分のパターンの変化と比較し、学習者が見て、聞いて、手に触れて、じぶんの進捗を実感できます。
このアプローチは、学習者に単純な総合点を提供する従来の方法とは異なります。エンパシームでは、無意識レイヤー①、②で気づかなかった、じぶんの無意識に起きている現象をふりかえれり、そのイメージを活かしてプラクティスに没頭できるからです。
いったん気づいて意識化したことを、実際にやって無意識化につなぐことがポイントです。知っただけでは使える知識にはなりません。
没頭できる、途切れのない「くりかえしとふりかえり」
エンパシームは、インナースピーチを育むのにふさわしいを環境(アフォーダンス)を提供します。
ワーキングメモリの制約である、2秒以内の短い対話フレーズをくりかえしまねて、音の出し入れに没頭し、それをふりかえる、途切れのない循環をつくります。
インナースピーチの発達に必要なワーキングメモリの制約にあわせたプラクティスは、脳内の処理能力を高めます。
また、プラクティスを周期的に継続することで、学習者は徐々に言語を内面化し、時間をかけて流暢さと、気づくセンスを身につけます。
インナースピーチを共有する
さらに、エンパシームはプラクティス共有プラットフォームを提供し、学習者はプラクティスを仲間と共有することで、互いにはげまし合い、忙しい日常生活の中で無意識に減衰しがちな心理的エネルギーを補給することができます。
インナースピーチは思いを育てる
エンパシームは、レイヤー①のプラクティスと、レイヤー②の自動的な認知プロセスの相互作用を促進し、インナースピーチの習熟度を向上させます。
インナースピーチは、ねがう心・目標意識を育て、くりかえし練習を持続させるために不可欠なものです。エンパシームは、このサイクルを通して、無意識の力を活用し、個人の無意識の力を最大限に引き出します。
エンパシーム英語トレイル
現在、エンパシームで英語習得を支援するプラットフォームをさらに充実させた「英語トレイル」を準備中です。「もう一歩、上達が進まずに悩む」多くの英語学習者に向け、無意識レベルの壁を壊し、脳内の再現力をつけるメソッドを提供して、上達の実感だけでなく、継続力を支えます。
社会に役立つトレイルづくりを目指して
エンパシームは、学習者だけでなく、教える立場、支援する方もご利用になれるプラットフォームです。学習者に知識を授け、教えることはできても「プラクティスをあげる」ことはできません。日夜、教育・指導に腐心なさっているEducatorの方々が、エンパシームを利用して、学習者のプラクティスを支援できます。
学習者に欠落しているインナースピーチ化の自習を助け、定量データを活かして成果を上げる一方、体系的に学習者の自習を管理・サポートするしくみを提供します。
エンパシームは、インナースピーチの促進に焦点をあて、無意識をデータとして活用することで、第二言語の学習に革新をもたらす可能性を秘めています。
そればかりでなく、この第二言語学習へのアプローチの可能性を追求し続けるうちに、この分野にとどまらない広範囲な応用も明らかになってくるでしょう。
従来、自己をふりかえりようにも、インナースピーチや無意識レベルのデータを活用できませんでした。エンパシームは、内なる対話と無意識の力を解き放ち、日常のプラクティス(実践)をデータに変え、洞察に結びつけます。
このように自己をふりかえることができれば、マインドフルネスから認知行動療法に至るまで、共感と思いやりの心を育むことが重要な分野での研究にも役立つはずです。
共感の最小単位「エンパシーム」
エンパシーム (Empatheme) という命名は、肉声の力、心のことば・インナースピーチによって、それがあたかも共感の力を引き出し、従来むずかしかった「互いに助け合うコミュニケーション」を実現する願いを込めています。プラクティスする人の身になって、働くテクノロジーを編み出し、AI時代に人間だからこそ発揮できる力を引き出し、社会に貢献することが目標です。