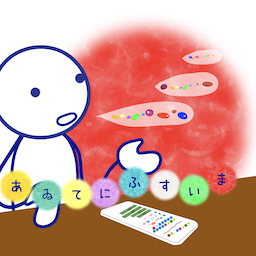
現代社会の価値尺度は、定められた時間の中でどれだけ多くの産出や処理ができ、得点がとれるか、という考え方だけが突出している。経済も教育も自己の評価も、成績は高いほうがよく、お金は多い方がよく、命は長い方 がよい、とされる。
外からものごとを測り、客観的に知ることの意義は否定されない。とすれば、「多ければ多いほどよい」ものの「見え方·聞こえ方・感じられ方」が変わるような、発想の反転をすることではないか。
それは過剰な情報やハウツースキルの中にあるのではなく、ふだん相手にせず に切り捨ててしまっている、じぶん自身の小さな時間の中にある。
谷川健一先生の最後のエッセイ『生命と寿命』(『海の宮・第6号』)の中に、そのヒントがある。

「ルソーは『エミール』の一節で次のように述べている。もっとも多く生きたひとは、もっとも長生きしたひとではなく、生をもっとも多く感じたひ とである。この言葉は神谷美恵子の『生きがいについて』から引用したものであるが、長生きしたからといって、多くを生きたことにならないことを 痛切に指摘しているのである。では、「多くを感じること」とは何か。私見によれば、それは宇宙に脈動し遍満する生命のリズムを感受することにほ かならない。」多くを生きるとは、多くを感じることである。」
私はこれまで、このことばに従って「多くを感じる」ことができるような手伝いや、手助けや、支え になる「ものやしくみ」について、独自の方法で探究を続けてきた。それは「エンパシーム」(Empatheme 共感の資源·素材·単位)というアイディアに結実し、じぶん自身で「より多くが感じられる」というきっかけや可能性を試す日々の実践を積んできた。 ありふれた日常の中の、ほんの小さなひと息の時間の中に「宇宙に脈動し遍満する生命のリズムを感受する」という瞬間はどのようにして現れるのか、それを思い出したり深めたりす るのか、じぶん自身のことについて、ほのかな察しがついてきたように感じられる。

「想像・共感のモーメントは多ければ多いほどよい」のは、それが単にたくさんあるから、ではない。それは、小さな繰り返しをじぶんでたくさん つくる過程で、きっかけができるからである。
未だ知らないじぶんという可能性が生まれるからである。その中にかけがえない宝ができる。それは、 たのしみ・よろこび·わかちあいの体験ひとつひとつであり、勇気や希望や信念のことばひとことひとことが生まれることである。
精神的な努力が実るために、ただひたすら頑張ればよいということでもなければ、何か特別な、マジカルな力が必要だということを言おうとしているのではない。自然なかたちで、素直なじぶんの姿勢を表す時·場の回数が連なりになれば、その連なりが意味をつくる。
ひとつひとつは、それぞれひとつに過ぎない が、連なり、繋がり、集まると、自然に重みづけや結びつけができ、そのありよう全体に意味が生まれる。自然のなりゆきに委ねるだけで、ひとつ・ふ たつ・みっつと数えられる素振りが繰り返され、つながれば、その中に、かけがえのないものが生まれるはずである。それは、確率的に、統計的に、数 理的に、じぶんという可能性が高まると言い換えても構わない。

大切なことはたったひとつ、素のじぶんが共感するひとときを「多く」思い出し、感じることである。安らいで、委ねて、じぶんの土壌から、想像の資源を採りだし、素材にすること。
共感するというエンパシーの力を引き出し、それを「より多く感じられる」ようにはからうために、人間の英知蓄積のひとつであるサイエンスの力も、創意工夫の結晶としてのテクノロジーの力も、そして何よりも、心身のふるまいの仕方(作法)というアートの力もあわせることはできるはずである。
しかし、生きるという人間のアートの手伝い·手助けとして、ともにいてくれるというテクノロジーを「過 剰・欠乏」の偏りから解放するのは、人間の心によるしかない。心がけや心構えは、頭だけではできない。身につける学びしかない。
本来、人間に備わった力「共感」を、ミニマル(不可欠最小限の)として、それをシンプル(簡素、ありのままの)に、小さな作法化をして身につけることこそ、 「過剰·欠乏」の文明社会を生きる、私たち地球上すべて人間にとって、感じられ方がかわる未知の可能性をもつ最もエッセンシャル(肝心要の、本 質の)なことだと思う。
共感の精錬 (11) サイエンス・アート・フィロソフィーをプラクティスに結いあわす へつづく
共感の精錬 目次ページ へもどる
