
意をこめて場面を演じよ
手本の声になれ

なりきるとは、手本の声になることです。リズムをまね、発音をまね、表情をまねる――これらが十分にできても、どこか手本とは違う印象が残ります。なぜでしょうか?
ものまね芸は、口調や言い回しだけではなく、声の響きまで似せて「本人が話しているような」印象を生みます。英語も同じです。声の大きさや息の吐き方、リズムや発音の先の、一歩踏み込んだ次元が「声の響かせ方」です。
肉声を響かせよ

声の響かせ方 (Voice Placement) は、ノドや口、鼻の中の声道(空気の通り道)の形や広さ、そしてその空間を通る空気の流れ(Airflow)によって決まります。
横隔膜が動くと肺の空気が押し上げられ、声帯 (Vocal cords) を通るとき、声帯はパタパタと開閉をくり返し、音のもととなる振動をつくります。ここで生まれるのは、まだ「声」ではなく、ブーという空気の振動音です。
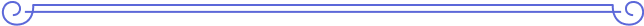

Become the voice.
(手本の声になれ)

声道と気流
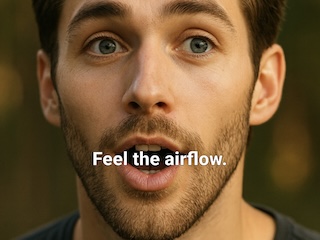
この振動はひとつの単純な波ではなく、声の高さ(Pitch)を決める大きな振動に、いくつもの小さな振動が重なった複雑な音の束です。この振動が声道を通る時に 共鳴 (Resonance) が起こり、母音がつくられます。
楽器に例えると、笛ではリード(薄い板)の振動が音源(声帯)、管の形や指の押さえ方が共鳴空間(声道)にあたります。
日本語は、口先でコンパクトに話すため、声道も気流も小さい運動スキーマが身についています。英語はその逆で、声道は広く、気流も大きいのです。そのため、声道を広げ、気流を増やすことで、声帯の振動がより力強くなり、これまで弱かった小さな振動成分にも共鳴エネルギーが乗り、母音の響きがくっきりと際立ちます。
リラックスとフロー

演じる質を高めるためには、まず、心を落ち着け、体をリラックスさせることです。筋肉の緊張をほぐし、「あくび」や「ため息」を使って気流を増やす練習が効果的です。声の大きさや息の強さだけでなく、声の出所とエネルギー供給(気流)をイメージすることが大切です。
そして何よりも重要なことは、じぶん自身が手本の声の主になりきろうとする心です。その思いがあるからこそ、日本語の運動スキーマ(自己流)をいったん手放し、没頭したフローの状態に入り、声の響きをより自然に再現できるようになります。あなたが「声になる」のです。
Put your heart in, become the voice.
(意をこめて 場面演じる 声になれ)

