
場面の意味を想像せよ
意味の認知スキーマ

ことばの意味は単語にある。単語を組み立てれば文になり、それが伝える表現になる。英単語に対応する日本語の単語を覚えることが英語学習、と教わってきませんでしたか?
違います。字面はまったく同じセリフでも、言い方が変われば意味は大きく変わります。例えば、Excuse me? は「すみません」という問いかけにもなり、相手の無礼を感じた場面では「ふざけるな」となります。Good for you. は「よかったね」という祝福、皮肉が込められると「勝手にすれば」と響きます。Are you sure? も「大丈夫?」という意味にも「本気なの?そんなわけないでしょ」という意味にもなります。
発話のニュアンス(パラ言語)

相手とのやりとりの場面や状況に応じて、声の調子や話し方が自然に変わり、受け取り方も変わります。その意味を生み出しているのが「コンテクスト」(ことばを取り巻く状況全体)です。
セリフの意味を決めるのは単語そのものではなく、その単語を含むコンテクストです。やりとりの状況が、話し手の感情や意図を生み、声の調子や表現を変化させます。その調子を通じて意味が立ち上がるのです。リズム、声のトーン、抑揚、間合いといったパラ言語的要素や、身振り・仕草・表情・場の雰囲気といった非言語的要素が重なり、「どう伝わるか」「どう聞こえるか」が、ことばの意味を形づくります。
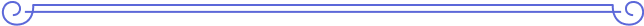

Context is meaning.
(意味はコンテクストに)

身ぶり・仕草・表情(非言語)

このように、音・イメージ・感情が結びついた場面体験を通じて形成されるのが意味の認知スキーマです。単語の意味を覚えるだけでは、音が聞こえず、イメージも湧かず、意味がピンとこないのは、この認知スキーマがまだ育っていないからです。
意味の認知スキーマを育てるには、場面を想像し、気持ちを込めてセリフを声にする練習が欠かせません。演じるつもりで声を出すと、自然にイントネーションもつきやすくなります。
セリフに情感をこめよ
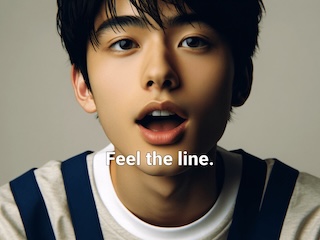
イントネーションは、声帯のピッチ(振動)を急激に変化させることで生まれる現象ですが、意識的にコントロールすることはできません。場面を想像して情感を込めることで初めて自然に現れるのです。文字に頼った音読は「棒読み」になりやすく、認知スキーマをつくる練習にはなりません。だからこそ、想像しながら声に出すことが必要なのです
Meaning is context.
(場を思え コンテクストに 意味宿る)

