
脳と体で身につけよ
音をまねて覚えよ

私たちは生まれて以来、お母さんの声を聞き、まねることで日本語を自然に身につけてきました。身につけるとは、脳が入力情報を処理し、それを身体で出力する「型」をつくることです。音や意味の認知スキーマ、顔や口の動きを支える運動スキーマはこうして形成されます。
第二言語習得も同じで、その言語の認知スキーマを獲得するプラクティスが必要です。聞こえない・言えない原因は、すでに身につけた母語の認知スキーマが干渉するためです。
認知スキーマのギャップ

母語と第二言語のスキーマの違い(ギャップ)を捉え、ボトルネックとなる「自己流のクセ」をつみへらしながら、セリフを再現するーそれが、音の認知処理と運動感覚を身につける唯一の方法です。
しかし、第二言語習得では、読み書き中心の学習で、始めることが多く「音をまねる」「リズムを似せる」といった基礎の体得が抜け落ちています。そのため、文字では理解できる簡単な文さえ、音声では聞きとれず、何を言っているのか分からない——この状態が必然的に生まれます。
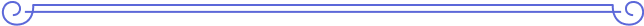

Mind the gap.
(ちがいにフォーカス)

自己流のクセをへらせ
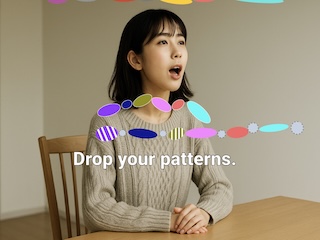
多くの人は、リスニングやスピーキングというと、ネイティブ音声を聞いたり、文を音読したりすることが練習だと思いがちです。ネイティブ音声をただ聞くだけでは、また、自己流の音読をするのでは、認知スキーマのギャップは縮まらず、「聞ける・話せる」状態には到達しません。
さらに、単語や文法の知識が聞く・話す力を支えると思われがちですが、リアルタイムで使える力には直結していません。文法は書きことばのルールであり、時間の流れを無視した分析上の概念です。たとえば、学校では「aやtheは名詞につける」と教わりますが、実際の会話では時間軸にそってaやtheを先に発声し、その後に名詞が続きます。後から付け加えることはできません。
ことばはリアルタイムの流れの中で次々と瞬時に起こる物理現象であり、同時に認知現象です。これは認知スキーマが働いて物事を瞬時に捉えられるからです。必要なのは、この流れに沿ったプラクティスです。
似せた度合いを測る

第二言語習得で不可欠なのは、いきなり「結果」をまねることではなく、ネイティブの幼児が身につけた基礎という原因をたどり、学ぶことです。
どんなに平易(=まねやすさのレベル)のセリフでも、それをどれだけ正確に再現できるかを測り、その度合いを高めていくプラクティスこそが、聞ける・話せる力を育む唯一の方法です。
Learning is replication by brain and body.
(ならうとは 脳と体で 身につけよ)

