
声でセリフを出し入れ
ことばの原点

私たちは、ことばを「文字の知識」として捉えがちです。けれども、ことばの原点は、相手とのやりとりの中で声を再現する「行為」にあります。文字で単語を覚えるのは学習の一部にすぎません。本質は、身体を通して声を発し、リズムや音の流れを脳と体で記憶する「運動行為」です。
単語をつなぎ合わせることで話せるようになるのではありません。話せるセリフがあって初めて、文として形になるのです。話すことも聞くことも一瞬の出来事で、発せられた音はその瞬間に消えていきます。私たちはその都度ワーキングメモリで音を保持し、脳と身体を協調させて「再現」しています。
声の運動を身体で覚えよ

ことばは、脳に文字で書き込まれた単語の在庫ではありません。その瞬間ごとに神経回路を発火させ、認知と運動のスキーマを働かせて、声という身体運動をリアルタイムに組み立てるのです。
そもそも「ことばを使える」とはどういうことでしょうか。食べる、歩く、聞く、話す——これらは母語なら誰もが100%無意識にできる動作です。少しでもズレれば成り立たないような、精密で連続的な身体運動です。
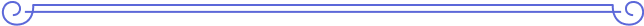

Words are act.
(ことばは行為)

セリフの100%再現が基本

そもそも「ことばを使える」とはどういうことでしょうか。食べる、歩く、聞く、話す——これらは母語なら誰もが100%無意識にできる動作です。少しでもズレれば成り立たないような、精密で連続的な身体運動です。
食べる行為が70%しかできない、歩く動作が80%しか再現できない、ということはありません。できるか・できないか、それだけです。そして、一度身についたら忘れることはありません。
この状態に最も近いのが、スポーツの基礎練習です。たとえば、パスやキャッチボールで「8割成功」では意味がありません。ボールは、100%相手に届き、確実にキャッチできて、初めてキャッチボールと言えます。
ことばも同じで、身体が無意識に反応し、100%近く相手に声を届けるレベルで初めて「使える」のです。脳神経の発火パターン(電気パルス)そのものが「記憶」されていきます。
言語の本質は共感

言語を「科目」として扱う学校教育では、文字に書かれた文や単語の意味を覚えることが中心になります。しかしこれは知識としてのことばであり、「ことばを使ってやりとりする行為」とは本質的に異なります。
ことばは「勉強」や「学習」というより、演技やスポーツに近いもの。知識以前に、声で、相手と音のやりとりを体得することが、言語の本質なのです。
Language is interaction enacted through voice.
(ことばとは 声の出入りと 心得よ)

