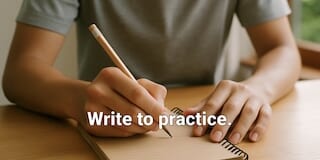書き出してズレをメモに
メモするプラクティス
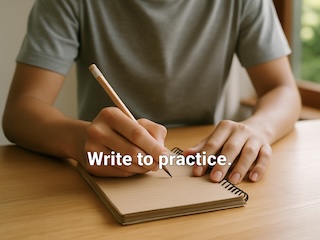
「どこがどう違うのか?どこまでできているのか?それをじぶんでよく見て、よく聞き、確かめる練習です。演じている最中はリアルタイムの動きなので気づけません。だからこそ、後から比べ、ズレを確かめてメモにするのです。
メモは、ラテン語の memor(記憶する・心に留める)に由来することばです。文字どおり、記憶に定着させ、気づきを誘発するためのものです。
ズレにフォーカスせよ
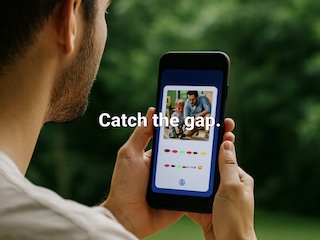
ここで大切なのは、自己判断で「良い・悪い」を決めることではありません。比べることです。何が同じで、何が違うのか。そのズレを一つひとつ見つけ、ことばにして書くのです。
「母音を伸ばしているつもりだった」「子音が弱かった」「手本の最初の音節はもっと短かった」など、セリフごとに一行のメモを書いてください。全部書くのではなく、選んで書きます。その一行が積み重なることで、あなたの脳は「気づく」回路をつくり始めます。
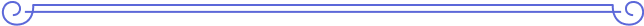

Write to practice.
(メモすることがプラクティス)

書くことで気づける

人間の脳は、すべての出来事を覚えてくれる装置ではありません。むしろほとんどのことを忘れるようにできています。だからこそ書き出すという出力によって記憶に刻まれ、後で思い出しやすくなるのです。
でも具体的に何を書いてよいのかわからない、手本とちがうことはわかるのだけれど…といったことがあるでしょう。でも実は、気づくから書くのではなく、書くことで気づけるようになるのです。書こうとすることで、頭の中にある曖昧な「もや」に形を与えられます。その時はじめて、記憶に留まる情報になります。その結果、後から「ああ、そういうことか」と腑に落ちる瞬間が訪れるようになります。
やりっ放しでは、練習の効果は得られません。メモをすること自体がプラクティスなのです。
自己観察のルーティン

「自分自身についてメモする」小さなルーティンが形になってはじめて、それが一貫して続いた時、それが初めて習慣と呼べるのです。
比べる、書き出す、気づくというループをを自己観察のルーティンにすることで、自分自身の練習の質を自覚できるようになります。その積み重ねは、「良い・悪い」といった自己判断スキーマから自由になり、目の前のズレを冷静に捉える力を育てます。そして、自分のプラクティス全体を見つめ直す力(メタ認知)へとつながっていくのです。
Review feedback and note the gap.
(書き出して ズレを目を寄せ メモにせよ)